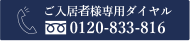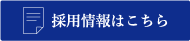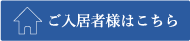最新コラム
- 2026.02.15 衆議院解散からみる今後の住まいづくり
- 2026.02.01 2026最大飛散量の花粉に備えて
- 2026.01.15 午年に思うこと「今年はウマくいく」
- 2026.01.01 金利上昇局面だからこそ、“今”住宅を考える意味
- 2025.12.15 湿度の正体、夏の40%と冬の40%は大違い
- 2025.12.01 なぜ空き家が延焼を拡大させたか
- 2025.11.15 2027年問題で変わる住宅―エアコンと蛍光灯の転換期
-
2025.11.01
アパート2代目オーナーの悩み
「引き継いだだけ」では続かない時代へ - 2025.10.15 実家じまい
- 2025.10.01 季節が飛ぶ「秋がない」住まいと日常の備え